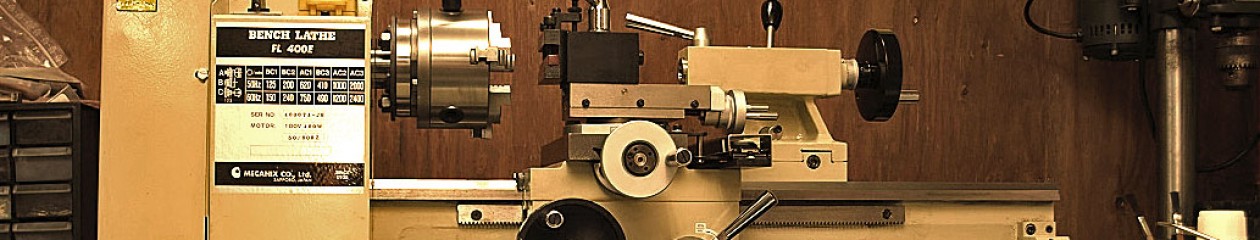作業前点検
作業前点検
 メッキ剥がれ
メッキ剥がれ
いつもご愛読ありがとうございます。今回は前回の続き、KTM 250EXC-Fのローダウン、フロントフォークに着手しました。オーナー様の体格に合わせて、ショート加工してスプリングも変更します。前後で-40㎜のローダウンですので、どちらにしてもスプリングの長さを変更しなければいけませんので、レート(強さ)もライダーに合わせます。
ローダウンするとネガな部分が出るでしょ?とお言葉を頂いた事があるのですが、弊社でローダウンした車両に乗って頂いた時に、これはネガな部分が無いね!と褒められた事がありました。自分の車両も必ずローダウンするんですが、前後バランスとモデルの癖(弱点?)を把握して改善する方向でローダウンすれば意外とネガな部分が出なかったりします。
モトクロスであればローダウンしたりはしないんですけど、エンデューロやクロスカントリーなんかですと小柄な方は必須だと思います。足が着く事で無駄な転倒が防げますし、それだけでもタイムアップしますからね。
 作業しながら点検
作業しながら点検
と、話が逸れましたがお預かりした車両を点検しながら分解していきます。フォークのインナーチューブにはメッキの剥がれがありました。今回はオーナー様と相談の元、様子見で再メッキや交換はせずに研磨して組上げる事になりました。本来ならば交換か再メッキが必要でしたが。
ハンドルの動きが重かったのでステムを点検してみると、ボルトがオーバートルクで締め付けられていました(^^;。国産と違ってステムベアリングは思いっきり締め付けてはいけません。念の為、取外しベアリングとレースを点検しました。無事でしたのでグリスを塗り込んで正しく組みつけました。
 カードリッジショート加工
カードリッジショート加工
 イニシャル確認
イニシャル確認
カードリッジをショート加工して、今回用意した長さを適切にしたスペシャルスプリングを使ってショート化します。念の為、イニシャル量(縮んだ量)を確認します。実はこの、スプリングのイニシャル量はサスペンションの動きに凄く影響します。
抜き過ぎても入れ過ぎても駄目で、適量のイニシャルを掛けておく必要があります。リアも同じです。この辺りを大きく間違えているライダーが多く見受けられますね(^^;
それぞれ信じている方法ってあると思うんですが理論的で実践的でなくてはいけません。精神論や雑誌等の噂では良いマシンにはできないと思います。硬いサスに乗らないとモトクロスでは上手くならないとか、エンデューロは柔らかい方が疲れないとか、訳が分かりません。
リジットサス?ほっぴんぐマシーン?ちょっと気〇がいじゃないか?あぁ~言い過ぎたアルヨ!
 完成
完成
今回はローダウンしましたが消耗した部品も交換してオーバーホールを兼ねた内容になります。オーナー様には足付性が良くなり、尚且つ本来の性能以上のマシンになる様にしました。
全てはバランスだと思うのです。